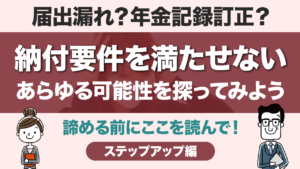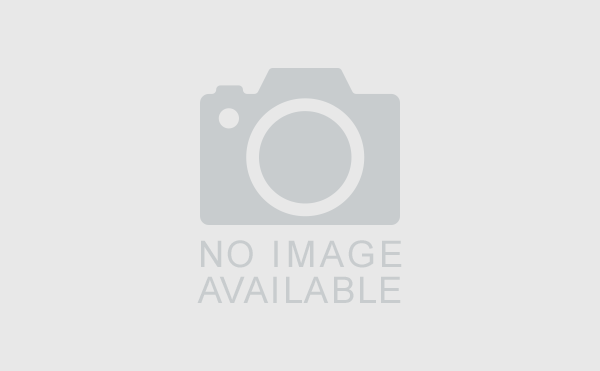障害認定日の概念
障害の程度は、障害認定日または事実認定日の障害の状態に評価されます。障害認定日という言葉から受ける印象により、普通の人は障害の程度を評価する基準となる日と考えてしまいます。しかし、障害認定日において障害の程度が評価されるのは、認定日請求の場合だけです。
障害認定日は、もともと健康保険における療養の給付期間、傷病手当金の支給期間と関連性をもっていました。法制定当時の障害認定日は、初診の日から1年を経過した日とされていました。これは健康保険法における結核の療養給付期間が1年であったことが原因です。
当時は結核が国民病といわれ、障害年金の対象で最も多かったのも結核による障害です。それで、健康保険法における療養の給付期間が満了となったときに、障害年金に引き継いでいくという考え方で障害認定日が設定されていました。障害認定日概念は、健康保険の給付期間と結びつけて作られた者であり、給付期間が満了すれば障害であるとみなし、そのみなし規定に基づいた日のことを指していました。
厚生年金に20年遅れで制定された国民年金の障害年金では、法制定当時は「傷病が治った日」を症状固定日とし、治っていない限りは障害年金の対象としませんでした。「障害擬制」の考え方が採用されなかったのです。国民年金法では、昭和39年8月1日に支給対象となる障害の範囲に結核・精神病等の内部障害が加えられ、このときにはじめて「障害認定日」概念が国民年金に持ち込まれました。
昭和29年に大改正がされた厚生年金保健法では、その当時の健康保険の療養の給付期間が3年とされていましたので、厚生年金の障害認定日も初診日から3年経過の日とされました。それにあわせる形で、国民年金も初診日から3年を経過した日が障害認定日と決められました。
障害認定日の原則と特例
障害基礎年金・障害厚生年金は、一定の障害の状態にあれば年金を支給することとなっています。一定の障害の状態になれば、いつでも請求できるということではなく、公平、公正で統一的な取り扱いをするため、決められた時期以外は基本的に請求できないこととなっています。法律で定められたこの時期のことを「障害認定日」といい、次のように定めています。
- 障害認定日の原則:障害の原因となった傷病の初診日から1年6ヶ月を経過した日
- 障害認定日の特例:障害の原因となった傷病の初診日から1年6ヶ月以内に治ったものは治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
障害認定日の特例の具体例
次の①〜⑦の場合は、初診日から起算して1年6ヶ月未経過であっても、下に書かれた日が障害認定日となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3ヶ月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁の装着をした場合は、装着した日
- 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日
- 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日
- 咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
- 脳血管障害による障害認定日は、6ヶ月以内は症状固定としない(脳血管障害は原則6ヶ月という誤解が、市町村の国民年金担当課などで広まっていますが間違いです。6ヶ月を経過した後の症状固定日というのが正しい理解です。)
障害評価の時期と事実認定日
「事実認定日」とは障害の程度を評価し、その程度が法に規定されている障害の状態に該当しているかどうかを定めるべき日のことを指します。もともとは「障害認定日」は障害の程度を評価する日でした。ところが、事後重症の制度がつくられた後は、障害認定日以外の日でも障害の程度を評価する日ができました。これが障害認定日と事実認定日を区別しなければならなくなった理由です。
| 年金の種類など | 障害の程度を実際に認定する日 |
| 20歳前初診 | 20歳到達時、20歳到達時以後に1年6ヶ月目が到来するときはその日 |
| 認定日請求 | 「障害認定日」 |
| 遡及請求 | 「障害認定日」と請求時 |
| 事後重症 | 請求時 |
障害認定日は、認定日請求の場合はその日の障害の状態を評価するのですが、事後重症などでは、障害認定日は単に年金額計算の基準となる日の意味しか持っていません。障害厚生年金の年金額は、障害認定日の属する当月までの月数で計算され、認定日の属する月の翌月以降は計算の対象に入りません。
事実認定日における障害程度の評価は、診断書に基づいて行われます。診断書の⑩欄「障害の状態」と書かれたすぐ右に赤色で(平成 年 月 日現症)と印刷されています。この日付がいつかを決めるのが事実認定日です。請求手続を進める上でこの日を確認しておくことは非常に大事なことです。