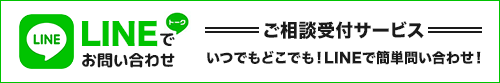生計維持関係の認定基準



生計維持関係の認定基準
「障害基礎年金の加算額の対象となる子」および「障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者」にかかる生計維持関係は、生計維持関係(受給権者の収入によって生活が成り立っている)等の認定日において、(1)生計同一要件および(2)収入要件を満たす場合に認定されます。

生計同一要件
生計を同じくしていた者又は生計を同じくする者(配偶者又は子)とは次のいずれかに該当する方をいいます。
生計同一認定対象者について
- 18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子
- 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する状態である子
- 65歳未満の配偶者
- 住民票上、同一世帯である
- 世帯を別にしているが、住所が住民票上、同一である
- 住所が住民票上、異なっているが、次のいずれかに該当
- 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
- 単身赴任、就学又は病気療養上等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、①生活費、療養費等の経済的な援助が行われている、②定期的に音信、訪問が行われているなどの事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

生計同一関係の確認方法
生計維持・生計同一関係は戸籍謄本、世帯全体の住民票、前年の所得証明等により審査の上認定されます。更に、加算対象者が受給権者と別居していたり、別世帯である場合は、別途、第三者の証明などの提出が必要となります。
- 住民票(世帯全員)の写し
- 別世帯となっていることについての理由書
- 同居についての申立書
- 第三者の証明
- 別居していることについての理由書
- 経済的援助および定期的な音信、訪問等についての申立書
| 事項 | 提出書類 |
|---|---|
| 健康保険の被扶養者になっている場合 | 保険証の写し |
| 給与計算上、扶養手当等の対象となっている場合 | 給与明細の写し |
| 税法上の扶養親族になっている場合 | 源泉徴収票の写し |
| 定期的に送金がある場合 |
|
| その他 | その事実を証する書類 |

生計同一者の扱い難しすぎない?
・世帯は一人で私が世帯主
・母から学費を"借りてる"
・婚約者と同棲していて生活費は折半
奨学金のこれどうしたらいいか誰もわかんないんだけど苦笑
機構に電話して聞かなきゃかな…— ◬Haruka◬ (@pyamz_24) 2019年11月6日
内縁/事実上の婚姻関係について
配偶者である夫および妻には、婚姻の届出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある者も含まれます。
事実上婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいい、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活を成立させようという合意および事実関係が認められるものをいいます。

適用除外者
夫婦としての共同生活を成立させようという合意および事実関係が認められる場合であっても、その関係が反倫理的な内縁関係である場合、事実婚関係とは認められない。具体的には次の通り。
民法第734条(近親婚)の制限
民法734条は、「直系血族又は三親等内の傍系血族」との間の婚姻を禁止しています。「直系血族」とは、自分と直系の関係にある人、具体的には、父母、祖父母、総祖父母、高祖父母…や、子、孫、曾孫、玄孫…といった人のことを指します。また、「傍系血族」とは、同じ祖先から分かれ出た人、具体的には、兄弟姉妹(同じ父母から分かれ出ている)、叔父、叔母、甥、姪、従兄弟姉妹、再従兄弟姉妹…(同じ祖父母から分かれ出ている)といった人のことを指します。
第735条(直系姻族間の婚姻禁止)
直系姻族は、姻族のうち、自己の配偶者の直系血族および自己の直系血族の配偶者のことをいいます。 … 例えば、夫から見て妻の父母・祖父母や、自分から見て子・孫の夫や妻などが直系姻族に該当します。 民法735条は、直系姻族間の婚姻は、たとえ姻族関係が終了してもすることができないとされています。
第736条(養親子関係者間の婚姻禁止)
普通養子縁組又は特別養子縁組をすると、その養子となった者と養親とは、民法上血族として取り扱われます(民法第727
条)ので、両者は結婚する事は出来ません。養親と養子との間の親子関係(直系血族関係)は、養子縁組の終了により解消し、元の赤の他人同士に戻る事になったとしても、親子関係が終了したとしても結婚する事は出来ません。(民法第736条)
離婚後の内縁関係と生計維持関係
離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取り扱いについては、当事者間に、社会通念上、夫婦としての共同生活を成立させようという合意および事実関係が認められれば、事実婚関係にある者として認められ、配偶者加算を受けることが出来ます。
重婚的内縁関係
届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合は、届出による婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定されます。なお、内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係がその実態を全く失ったものとなっているときを除き、先行する内縁関係における配偶者を事実婚関係にある者とされます。

- 当事者が離婚の合意に基づいて夫婦としての共同生活が行われていない場合であって、その状態が長期間(おおむね10年程度以上)継続し、当事者双方の生活関係がそのまま固定していると認められるとき
- 「夫婦としての共同生活の状態にない」といい得るためには、次に掲げるすべての要件に該当することを要するものとすること
- 当事者が住居を異にすること
- 当事者間に経済的な依存関係が反復して存在していないこと
- 当事者間の意思の疎通をあらわす音信又は訪問等の事実が反復して存在していないこと
重婚的内縁関係に係る調査
重婚的内縁関係にある者を「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として認定するには、届出による婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっていることを確認するため、戸籍上の配偶者、内縁関係にある者に対して、次の調査を行い、その結果を総合的に勘案して事実婚関係の認定を行うものとされています。
- 別居の開始時期及びその期間
- 離婚についての合意の有無
- 別居期間中における経済的な依存関係の状況
- 別居期間中における音信、訪問等の状況
- 1による調査によっても、なお不明な点がある場合には、内縁関係にある者に対しても調査を行う。
親の年金請求の手続きやってるんだけど、事実婚だからめっちゃめんどくさい😕💭「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」書いた🤣戸籍謄本は2つ(父母)ないと家族全員揃わないし、夫婦別姓ちゃんと法律で認められてほしい🥺昔、わたしの世代では認められてるといいねって話してたけどまだだね〜
— miho (@mihohagi) 2019年10月8日
事実上の親子関係について
子は、実子または養子のみが認められ、事実上、親子関係にある者は、子とは認められません。
収入要件
加算対象者の収入について
生計維持認定対象者は、次のいずれかに該当する者とされます。
- 前年の収入が年額850万円未満
- 前年の所得が年額655.5万円未満
- 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記1又は2に該当すること
- 前記の1、2又は3に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること


収入の確認方法
前年の所得証明等の提出が必要です。もし、障害認定日が5年以上前で所得の証明が取れない場合は、「収入に関する申立書(任意の書式)」を作成し、提出する必要があります。
生計維持関係等の認定日
- 受給権発生日
- 障害年金の受給権発生後において、当該受給権者が次のいずれかに該当することとなった日
- 障害年金加算改善法施行日の前日において、加給年金額及び加算額の加算の対象となっていない配偶者及び子を有する場合は、法施行日の前日(平成23年3月31日)
- 法施行日以後において、新たに生計維持関係がある配偶者及び子を有するに至った場合にあっては、当該事実が発生した日
- 法施行日以後において、加給年金額及び加算額の加算の対象となっていない子を有する場合にあっては、その子が新たに障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態となった日。
- 法施行日以後において、加給年金額及び加算額の加算の対象となっていない子を有し、受給権者の配偶者等に対して当該子に係る児童扶養手当が支給されている場合にあっては、児童扶養手当の額が決定、改定又は停止となった月の前月の末日、若しくは障害基礎年金又は障害年金の当該子に係る加算の届出日。
よくあるご質問

障害等級1級または2級の障害状態にある加算対象の子の障害認定はどのように行われるのですか?
障害年金用診断書の提出により行われます。また、子の障害に関しては、障害認定日という概念がないため、初診日から1年6か月を待つ必要はありませんし、更新も必要ありません。
まとめ
以上、生計維持関係の認定は、上記の「生計同一」「収入」という2つの要件を満たしたときに認められます。
別居(住民票が別)や事実婚の場合、金銭の授受や音信のやりとりが残っていないかの確認ができるかどうかで加算の対象となるか否かが判断されますのできちんと証明するものを準備されることをお勧めします。